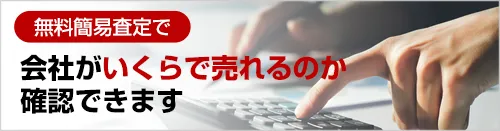【2025年最新版】グループホームの売却・M&A完全ガイド~認知症対応型共同生活介護の売却・譲渡を成功させるために~

グループホームの事業売却を検討されている事業者の皆様へ、本コラムでは、グループホームのM&A(事業譲渡・売却)を成功させるための実務的なポイントを、最新の業界動向や実際の成約事例を交えて詳しく解説します。
【目次】
グループホームとは
グループホーム(共同生活住居)は認知症を持つ高齢者の方を専門に受け入れる小規模介護施設です。地域密着型サービスの一つで、要介護認定を受けた高齢者の方が、住み慣れた地域で生活を継続できるようなサービスを提供しています。入所施設ではなく居宅施設に位置付けられます。
グループホームでは5人以上9人以下を1ユニットとして2ユニットまで(用地確保が困難な地域では3ユニットまで)、原則個室、さらに1ユニットごとに共用の居間、食堂、台所、浴室を設置し、消火設備や災害時対応設備を整備する必要があります。バリアフリーにも対応しなければなりません。また地域住民との交流を図ることができるよう、住宅地に設置されることが基本です。
グループホームは認知症を持つ高齢者の方に特化した介護施設のため、入居するには、65歳以上であること、要支援2又は要介護1以上の認知症患者であること、及び施設と同一地域内の住人であることが必要となります。
| 1事業所あたり |
1事業所あたり1又は2の共同生活住居(ユニット)を運営 ※地域の実情により効率的運営に必要と認められる場合は、3つの共同生活住居を設けることができる。 |
| 1ユニットの定員 | 5人以上9人以下 |
【設備】
| 立地 | 住宅地等に立地 |
| 居室 | 7.43㎡ (和室4.5畳)以上で原則個室 |
| その他 | 居間・食堂・居間・台所・浴室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備 |
【人員配置基準】
| 介護従事者 |
日中:利用者3人に1人(常勤換算) 夜間:ユニットごとに1人 |
| 計画作成担当者 | ユニットごとに1人(最低1人は介護支援専門員)※ユニット間の兼務はできない。 |
| 管理者 | 3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従 |
グループホームにおいては、看護職員の配置義務はありません。ただし、医療機関との連携体制を整備することが望ましいとされています。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、入居者に対して適切な介護サービスを提供するため、上記のような基準が設けられています。
出典:厚生労働省 認知症対応型共同生活介護
グループホームのM&Aが注目される背景
グループホーム業界は、高齢化が進む日本社会において今後も一定の需要が見込まれる分野です。しかし、当センターにはグループホーム事業者の方々から、施設の売却・譲渡に関するご相談を日々受けており、人材不足や物価高騰、利用率の低下などにより、事業の継続が困難になっている事業者が増えているのが実情です。
実際、WAM(福祉医療機構)の調査によれば、平均利用率は前年より低下し、待機者数も減少傾向にあるほか、家賃・光熱費・食費などの利用者負担額が上昇しており、価格競争の激化が経営を圧迫しています。また、人件費率の上昇や介護人材の確保難も深刻化しており、特に小規模施設では収益性の確保が難しくなっています。
背景①:利用率の低下と待機者数の減少
調査によると、グループホームの平均利用率は2022年度94.9%から2023年度94.5%へと微減しており、待機者数も減少傾向にあります。地域によっては競合施設の増加や有料老人ホームへの流出もあり、安定した利用者確保が難しくなっていることが経営課題となっています。
背景②:物価高騰による利用者負担の増加
利用者の月額負担額(家賃・水道光熱費・食費など)は前年よりも増加しており、特に家賃は平均で約7,600円上昇しています。これにより、利用者の選択肢が広がる一方で、価格競争が激化し、経営の安定性に影響を与えています。
背景③:人件費の上昇と人材確保の困難
介護職員の処遇改善加算や物価高騰の影響により、人件費率は69.2%から69.4%へ上昇しています。一方で、介護人材の確保は依然として困難であり、特に地方や小規模施設では採用難が深刻化しています。
背景④:ユニット数による収益格差
調査では、ユニット数が多い施設ほど利用者単価や収益性が高い傾向が示されています。1ユニット施設と比べて、3ユニット以上の施設では月額利用者負担額やサービス活動収益が顕著に高く、規模の経済が働いていることがわかります。このため、小規模施設が大規模法人に吸収されるM&Aが進む構造的背景があります。
こうした背景のもと、グループホーム業界は今まさにM&Aによる再編の時期を迎えているといえるほど、事業の統合・譲渡が活発に行われています。
グループホームM&Aの特徴3選
グループホームM&Aの特徴①~建物・土地の契約形態と地代家賃率~
グループホームは多くが賃貸物件で運営されており、地代家賃率が経費に大きく影響します。厚労省所管の調査でも、地代家賃率が高い施設ほど赤字傾向が見られ、特に都市部では注意が必要です。M&A時には、建物の契約形態(賃貸・所有)や更新条件、原状回復義務などを精査し、将来的なコスト増加リスクを見極めることが重要です。
グループホームM&Aの特徴②~地域包括支援センターやケアマネとの関係性~
グループホームは地域密着型サービスのため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との信頼関係が利用者紹介に直結します。M&Aによって運営法人が変わると、地域との関係性がリセットされる可能性があり、利用率の低下につながることも。買収側は、既存の地域連携体制を尊重し、職員や地域との関係維持に配慮する必要があります。
グループホームM&Aの特徴③~指定更新・加算取得の引き継ぎに注意
グループホームは介護保険制度に基づく「指定事業所」であり、運営法人が変わる場合は指定の再取得や変更届が必要になることがあります。特に、認知症介護実践者研修修了者の配置や看取り体制加算の取得状況など、加算要件を満たす人材や体制が引き継がれるかどうかが重要です。M&A後に加算が取得できなくなると、収益構造が大きく変化するリスクがあります。

グループホーム事業者がM&Aを選ぶメリット
グループホームM&A(売却・譲渡)の特徴やメリット・デメリットをご紹介します。
グループホーム事業の売却・譲渡を検討している売り手は、近年の人材不足や物価高騰による運営コストの増加、利用率の低下などにより、事業の継続が困難になっている事業者様や、将来的な事業承継に向けて後継者の選定に難航している事業者様からのご相談が多く寄せられております。
一方、買い手となる介護事業者様は、地域密着型サービスとしてのグループホームの価値を重視し、地域内でのシェア拡大や人材確保の優位性を活かして、M&Aによる事業拡大を進めたいというご要望をいただいております。
【M&Aを選ぶメリット(売り手側)】
・事業承継の選択肢が広がる
→後継者がいなくても、第三者への譲渡により施設運営を継続できる。
・職員と利用者の安心を守れる
→雇用やケアサービスが維持されることで、現場の混乱を最小限に抑えられる。
・経営者のリスク軽減と資産整理
→個人保証の解消や創業者利益の確保により、経営者の負担が軽くなる。
・法人グループによる支援体制の活用
→加算取得、人材採用、業務効率化など、経営基盤の強化が期待できる。
・ライフプランの柔軟化
→早期引退や他事業への集中など、経営者の人生設計に余裕が生まれる。
【M&Aを選ぶデメリット(売り手側)】
・現場への説明と理解形成が必要
→グループホームは家庭的な雰囲気を重視するため、職員や利用者への丁寧な説明が不可欠。誤解や不安を防ぐためには、事前の情報共有と信頼関係の維持が重要です。
・運営方針の変化による影響
→買収後に法人の方針が変わることで、ケアの質や職場環境が変化する可能性があります。
特に認知症ケアや看取り体制など、施設の特色に関わる部分は慎重なすり合わせが必要です。
・制度・加算・指定の引き継ぎリスク
→介護保険制度に基づく指定事業所であるため、加算取得状況や人員配置要件の維持が重要。引き継ぎが不完全だと、収益構造に影響が出る可能性があります。
デメリットに対しては専門的な知識を持ったM&A仲介会社であれば先回りして対策をしてくれるので、大きく心配する必要はないと言えます。グループホームのM&Aは、経営課題の解決と地域福祉の継続を両立できる選択肢の1つであると言えます。
グループホームの売却価格の相場は?
各業態により評価の仕方が変わってくるため、売却価格の相場が何円ですとは明確にお伝えができません。ここでは評価のポイントをお伝えします。具体的な金額が知りたい方は、企業の売却価格を査定できるサービスを提供している仲介会社が多くありますので、そのようなサービスの利用をお勧めします。
・利用者数・稼働率・営業利益
(入居率90%以上、営業利益が安定して黒字など)
・人員体制
(認知症介護実践者研修修了者が複数在籍、夜勤体制が安定など)
・地域の介護需要と競合状況
(高齢化率が高く、競合が少ないエリア)
・賃貸条件・行政指導歴の有無
(家賃が適正で長期契約、原状回復義務が軽いなど)
(指導歴なし、監査対応が良好など)
特に買い手が重視することが多いのは「入居率」「加算取得」「人材の安定性」「地域性」の4点です。しかし、評価基準に当てはまらないから売却できないということもなく、エリアや事業内容に魅力を感じられる買い手も多くおられますので、ご不安がある場合はM&A仲介会社へ問い合わせてみましょう。
どのくらいの譲渡額が付くのか、60秒で簡単無料査定!
グループホームのM&A成約事例ピックアップ
当センターで実際にM&Aを経験された、グループホームの事業者様へインタビューを実施させていただきました。経験者の生の声だからこそ参考になるのではないかと思います。是非ご覧ください。
グループホームのM&A成約事例
地域密着型の代表格である、グループホーム/小規模多機能の買収成約事例
全国に複数の介護施設を有する株式会社アルテディア様は、今後都内で事業所を拡大していく方針で、その足掛かりとして2018年7月1日に江東区にて「ファンライフ江東(グループホーム/小規模多機能)」の運営を開始しました。同社は、千葉県で1915年設立され103年の歴史をもつ株式会社博全社を母体としております。同グループのM&Aに関わる基本方針は、「結婚をすること(M&A)が目的ではなく、結婚をした後に皆が幸せになることが目的」つまりは『グループインした後の従業員、取引先、顧客、地域社会、株主の幸せの最大化』を目的に、皆にとってプラスとなるM&Aを行っていきたいと考えておられます。
成約事例インタビューをもっと読む
他にも介護業界のM&A・売却・譲渡に成功された経営者様のインタビューを多く掲載していますのでご覧ください。
インタビューをもっと読む
まとめ
今回のコラムでは、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)のM&A(売却・譲渡)について、グループホームのM&Aにお悩みの経営者の皆様にむけ、特徴やメリット・デメリット、事例をご紹介しました。
グループホームのM&Aについてお悩みの場合はぜひ、介護業界特化のM&A仲介、介護M&A支援センターにご相談ください。