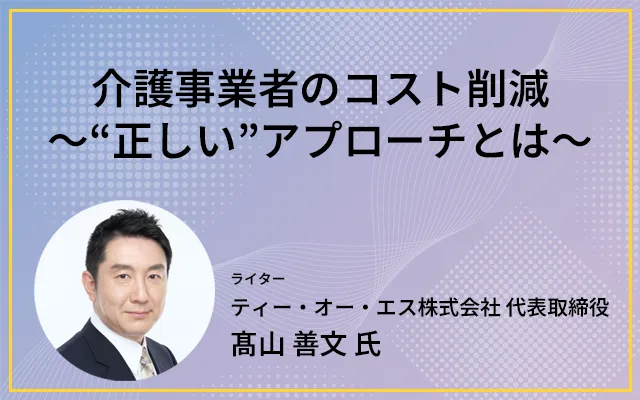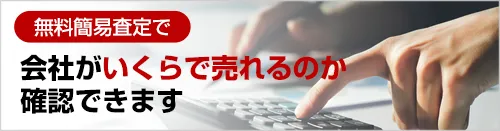連日の酷暑、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
高齢者の中には「電気代がもったいないから」とエアコン使用を控える方もいます。しかし、介護施設の運営では、入居者の健康と安全を守るため、空調を止めるわけにはいきません。
私が支援している事業所にも、太陽光パネル設置や電力会社変更、省エネ機器導入など、毎日のように営業案内が届きます。光熱費は日々の運営に直結する大きなコストということはわかっていても、「何から手を付けたらよいのか…」という思いではないでしょうか。
ご存じの通り、介護事業の多くは売上の大半を介護報酬に依存しています。報酬単価が大幅に引き上げられる環境ではない以上、「コスト構造の最適化」こそが経営安定の鍵です。
とはいえ、私たちがよく目にするコスト削減の情報には、広告色の強い“成功事例”が多く見られます。導入すれば誰でも劇的に削減できるかのように語られていますが、それが自社に本当に有効かどうかを見極めるのは容易ではありません。
そこで本稿では、営業トークに振り回されないために、公的データとエビデンスに基づく「正しい」コスト削減の考え方と、介護現場に即した実践のポイントを整理してみたいと思います。
1. コストのツボはどこに?
介護事業の経営者の方はご存じかと思いますが、厚生労働省「介護事業経営実態調査」や福祉医療機構の分析によれば、介護事業の費用構成は大きく次の3つに分けられます。
- ・人件費
- ・減価償却費
- ・光熱水費
まずは自社の費用構成を把握することが第一歩です。その際には「介護事業経営実態調査結果」や福祉医療機構が公表している各サービスの経営状況を参考に、全国中央値との比較を行いましょう。そこから、どの費用項目に削減余地があるかを明確にすることが重要です。
(参考資料)
厚生労働省「令和5年度 介護事業経営実態調査結果」
独立行政法人福祉医療機構「経営サポート事業」
ここで「光熱費」に注目してみましょう。
東京都の省エネ診断によれば、介護施設における電力消費の大半は「照明」と「空調」です。
この2つの更新や運用改善は、費用対効果が高く、省エネ効果も数値で示しやすい分野です。さらに、資源エネルギー庁や環境省などの補助金制度を活用することで、投資回収期間を短縮できます。
(参考資料)
東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター, 介護施設の省エネルギー対策

2. 光熱費削減のための基本ステップ
「光熱費」の削減は、更新投資と日々の運用改善を組み合わせることで成果が出ます。特に小規模事業所では、まず「運用改善」から始めるのが現実的です。
① エネルギー使用量の見える化
毎月の使用量をグラフ化して職員が目にする場所に掲示。電気料金の領収書コピーでも十分効果があります。
② 目標設定
「前年同月比で1%削減」など、誰もが意識しやすい数値目標を設定。小さな数値でも継続がカギになります。
③ 定期検証と改善
効果を確認し、改善点を職員間で共有。小さな成功体験を積み重ねることが、継続と定着につながります。
(参考資料)
日本照明工業会が紹介する事例では、誘導灯のLED変更事例が挙げられています。
(一社)日本照明工業会 LED照明リニューアル事例
3. 即効性のある省エネ対策とは?
チェックリストで見直す運用改善
| 項目 | 具体策 | 実施状況 |
|---|---|---|
| 空調運用改善 | 室温28℃を目安に設定(※注) | ☐ |
| 温湿度計で確認しながら、扇風機やサーキュレーターで温度ムラを解消 | ☐ | |
| フィルター清掃で年間5〜10%の省エネ効果 | ☐ | |
| 照明管理 | 不要エリア・日中はこまめに消灯 | ☐ |
| スイッチのエリア分け表示で管理を徹底 | ☐ | |
| 厨房・給湯 | 冷蔵庫温度の適正化、扉開閉回数の削減 | ☐ |
| ボイラ燃焼空気比の調整や配管保温 | ☐ | |
| 共用部・トイレ | 暖房便座の節電モード活用 | ☐ |
| 待機電力削減 | 使用していないOA機器や自販機の電源オフ | ☐ |
※注意:「エアコン28℃」の誤解と正しい理解
・環境省が推奨している「28℃」は エアコンの設定温度ではなく、室温の目安
・実際の室温は、部屋の広さ・外気温・機器性能によって変動
・温度計・湿度計で室温を確認しながら調整することが重要

4. まとめ
- ●即効策:空調や照明の「運用改善」から着手(今すぐ始められる)
- ●中期策:LED照明や高効率空調機への更新
- ●長期策:補助金活用と更新時期をリンクさせた設備更新計画の策定
コスト削減とは、単なる支出カットではなく、「限られた経営資源の最適配分」です。
その中でも光熱費削減は、「取り組みをすぐ始めやすい」「効果が数値で見えやすい」
「職員と一体で進めやすい」というメリットがあります。経営改善と事業価値の向上を同時に実現するために、今こそ 計画的な省エネとコスト最適化 に踏み出してみてはいかがでしょうか。
<筆者のひとりごと>
前回のコラムでは「SNSショート動画を使った採用手法」を紹介しましたが、実際に世の中の動画を見てみると、「あれ?本人ちょっと無理してない?」というものも結構あります。仕事なので仕方なく自己紹介させられてる感じです。
やはり、大事なのは“職員に任せること”だと思います。若い職員が自分たちのノリで、楽しそうに撮っている方が断然よく、自然体の空気感こそが見る人に伝わる、と私は思います。
ここでちょっと思い出したいのが「メラビアンの法則」です。人が受け取る印象のうち、言葉は7%、声や話し方が38%、表情や仕草が55%を占める――要は「楽しそうに見えるかどうか」が勝負なのだと思います。
作り込まれた台本や演出より、現場の笑顔や自然なやり取りの方が、求職者にとっては何倍も魅力的に映るはずです。楽しく撮っている様子は、見ている側にしっかりと伝わるのではないでしょうか。
前回のコラムは下記クリックで閲覧可能です。是非ご覧ください。
「求人が来ない」を変える!SNSとショート動画で変わる採用のかたち
【参考文献】
独立行政法人福祉医療機構,2024,「社会福祉法人経営動向調査の概要」
環境省ZEB事例集(検索窓にて“介護施設”などの検索が有効)




 髙山 善文 氏
髙山 善文 氏