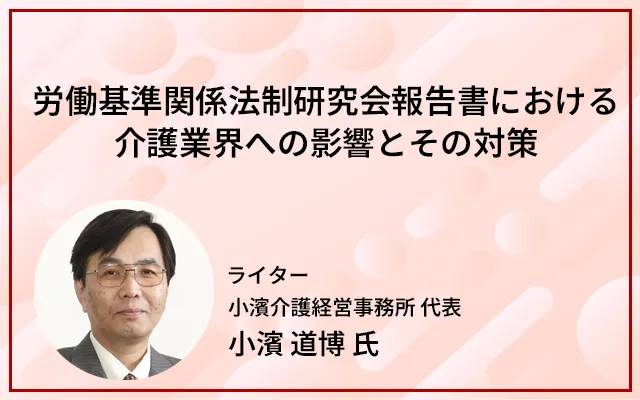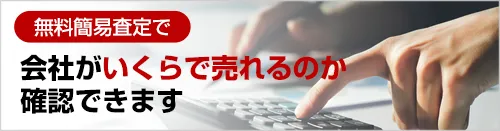【目次】
1.約40年ぶりの労働基準法大改正が示す方向性
2025年1月8日、厚生労働省の労働基準関係法制研究会から報告書が公表された。この報告書は約40年ぶりの労働基準法大改正の方向性を示すものであり、介護業界にとって看過できない重要な内容を含んでいる。
研究会では2024年1月から全16回にわたって検討が重ねられ、働き方の多様化、副業・兼業の増加、ICT活用の拡大といった社会変化に対応した労働法制の見直しが議論された。コロナ禍以降の行動変容により、従来の働き方の常識が根本から問い直される中で、労働基準法も時代に即した変革が求められている。
介護業界は慢性的な人材不足に直面している。厚生労働省の推計によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人の介護職員が不足すると見込まれている。有効求人倍率は4.20倍と全職種平均の3倍以上に達しており、1人の求職者を4社で取り合う激しい競争が続いている。このような状況下で迎える労働法制の大幅な見直しは、介護事業者にとって大きな転換点となる可能性が高い。
ただし、今回の報告書は研究会による提言段階であり、具体的な法改正の内容や時期については今後の労働政策審議会での議論を経て決定される。報道では2026年6月頃の改正法成立、2027年4月からの施行が予想されているが、これらは現時点では見通しに過ぎない。
2.介護業界特有の労働者性問題への対応
報告書の重要なポイントの一つが労働者概念の見直しである。一般的には業務委託やプラットフォームワーカーの労働者性拡大が議論されており、これまで業務委託として扱われていた人材も、一定条件下で労働者として取り扱われる可能性が検討されている。
しかし介護業界の実情は他業界と大きく異なる。厚生労働省通知により、介護サービスは雇用契約または派遣契約による職員のみが提供可能とされており、業務委託による直接的な介護サービス提供は制度上禁止されている。これは利用者の安全確保と継続的な責任体制の確保を目的とした重要な規制である。従って、他業界で問題となっているウーバーイーツ配達員やフリーランスエンジニアのような労働者性の判断問題は、介護業界では基本的に発生しない。むしろ、介護業界は既に適正な雇用関係を確立しているため、今回の法改正においては安定した基盤を持っていると評価できる。
ただし、間接業務である清掃、調理、事務などの業務で業務委託を活用している場合は注意が必要である。これらの業務についても労働者性の判断基準が厳格化される可能性があり、契約形態の見直しが求められる場合がある。

3.副業・兼業時代の労働時間管理革命
報告書が示すもう一つの重要な変更点が労働時間管理の厳格化である。特に副業・兼業における労働時間の通算管理が義務化される方向性が示されており、介護業界への影響は極めて大きい。
介護職員の副業・兼業は一般的に行われており、他の介護事業所との掛け持ち、介護関連の講師業務、夜間のコールセンター業務などが典型例である。これらの労働時間を通算して管理し、時間外労働の上限を超えないよう配慮することが事業者の義務となる見込みである。
さらに注目すべきは、研究会から13日超の連続勤務禁止が提言されていることである。現行法では理論上最大12日の連続勤務が可能とされているが、これを13日超で禁止すべきとの提言がなされた。24時間365日のサービス提供が求められる介護現場では、人手不足により長時間の連続勤務が発生しがちであるため、この提言が法制化された場合はシフト管理の根本的な見直しが必要になる。
対応策として、複数勤務先での労働時間をリアルタイムで把握できるクラウド型勤怠管理システムの導入が急務である。スマートフォンアプリを活用した訪問サービスでの正確な労働時間把握も重要になる。

4.業所運営における責任範囲の明確化
複数拠点やグループ運営を行う法人にとって重要なのが、事業単位・責任範囲の再定義である。現行法では事業場単位での労務管理が原則とされているが、テレワークの普及や働き方の多様化により、その適用範囲の見直しが検討されている。
介護業界では、本部機能と各事業所、訪問サービスと施設サービスなど、多様な事業形態が存在する。どの範囲まで労務管理責任を負うのか、事業所単位なのか法人全体なのか、その判断により運営体制の見直しが必要になる可能性がある。
5.政府支援を活用したICT導入戦略
ICT・介護ロボットの導入も効果的な対応策である。記録時間の30%削減、夜勤巡回回数の50%削減といった定量的な業務効率化が各所で報告されている。政府も介護テクノロジー導入に対して手厚い支援を継続的に提供しており、補助率最大80%の支援制度が活用できる。
2025年度については、地域医療介護総合確保基金および2024年度補正予算の繰越分を合わせて、大規模な支援が予想されるが、具体的な予算額については正式な発表を待つ必要がある。対象機器には、タブレット、クラウドサービス、インカム、Wi-Fi機器などが含まれ、包括的な支援が期待される。
ただし機器導入だけでは成功しない。職員研修とマニュアル整備が成功の鍵であり、ICTリテラシー習得のための継続的なサポート体制が不可欠である。導入時の研修はもちろん、継続的なサポート体制の構築が、投資効果を最大化するための必須要件となる。
ICTに関する記事はこちら
介護事業者必見!介護業界のICT化のポイントとは?
6.段階的な組織変革アプローチ
今回の労働基準関係法制研究会報告書は、介護業界にとって規制強化ではなく競争優位確立の機会として捉えることができる。報告書の内容が実際の法改正にどの程度反映されるかは今後の動向を注視する必要があるが、先行して対応することで、人材確保と定着率向上を実現し、持続可能な事業運営の基盤を構築できる。変革への準備は今から始めることが重要であり、段階的なアプローチによる小さな改善の積み重ねが、将来の大きな成果につながるのである。




 小濱 道博 氏
小濱 道博 氏