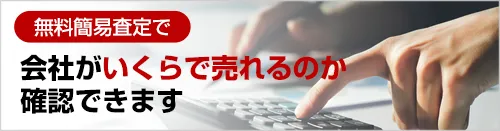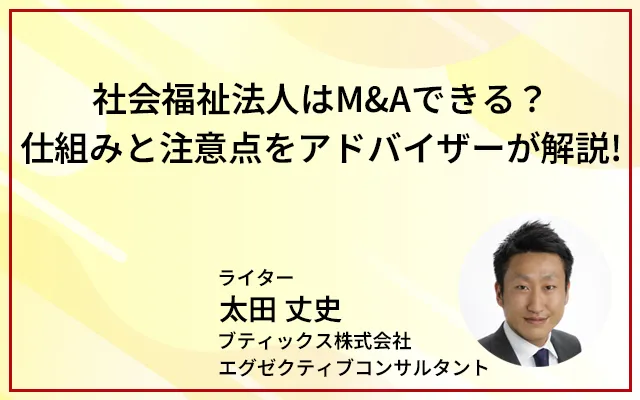
当センターでは、社会福祉法人の理事長から、社会福祉法人はM&Aできるのか、社会福祉法人のM&Aの流れは通常のM&Aと異なるのかという質問を日々受けています。
今回のコラムでは、社会福祉法人の理事長の皆様に向け、社会福祉法人のM&Aのポイントを解説いたします。
社会福祉法人の概要
良くご存じの内容かと思いますが、おさらいとして社会福祉法人の概要を解説いたします。社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて設立される非営利法人であり、社会福祉事業をおこなうことを目的とします。 ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。また、社会福祉法人は、社会福祉事業の他、公益事業及び収益事業を行うことができます。
- 特別養護老人ホーム
- 児童養護施設
- 障害者支援施設
- 救護施設 等
- 保育所
- 訪問介護
- デイサービス
- ショートステイ 等
社会福祉法人と株式会社の最も大きな違いは、営利を目的とするかどうかです。株式会社は利益追求が目的ですが、社会福祉法人は営利を目的とせず、福祉事業を通じて公共の利益に貢献します。 この違いがあるため、事業の譲渡においても注意すべきポイントが株式会社とは異なるのです。

社会福祉法人はM&Aできる?
社会福祉法人においても、一定の条件下でM&Aが検討可能です。ただ、株式会社の譲渡とは異なる注意するべきポイントがあるため詳しく解説します。
社会福祉法人の将来の選択肢として①合併②事業譲渡③社会福祉連携推進法人の3つがあげられます。
| メリット | デメリット | |
| 合併 | 後継者不在・法人が抱える悩みを一気に解消 | 手続きが複雑で、参考事例も少ない |
| 事業譲渡 | 譲渡したい事業のみを選択して譲渡することが可能 | 補助金の継承や契約の整理が複雑になる場合がある |
| 社会福祉連携推進法人 | 法人が抱える悩みを規模の大きさを活かした形で解消することができる | 連携推進法人の認定を受けている法人が少なく、統合相手の選択肢が少ない |
合併は法人単位での統合を意味し、財務や人事の一本化が可能ですが、文化の違いやPMI(統合プロセス)の負荷が課題となることもあります。
一方、事業譲渡は施設やサービスのみを別法人へ移す形になるので、合併ほどの負荷はありません。柔軟性がありますが、補助金の継承や契約の整理など、個別交渉の難易度が高くなる傾向があります。
社会福祉法人には社会福祉連携推進法人という選択肢も
合併はハードルが高いとお考えの方には、社会福祉連携推進法人という選択肢もあります。
社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。2社以上の社会福祉法人等が社員として参画し、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することを目的としています。
社会福祉連携推進業務は大きく6つに分類されています。
- ① 地域福祉支援業務
- ② 災害時支援業務
- ③ 経営支援業務
- ④ 貸付業務
- ⑤ 人材確保等業務
- ⑥ 物資等供給業務
M&Aを検討されている理事長の方から特に問題として伺うことが多い、経営と人材確保について、社会福祉連携推進法人の場合どのように活用できるのかご紹介します。
③ 経営支援業務- 社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施
- 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施
- 社員の財務状況の分析・助言・ 社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援
- 社員の特定事務に関する事務処理の代行等
例えば小規模事業者でICTの活用がままならない事業所などは、その原因として有識者の不在を上げています。社会福祉連携推進法人を設立することで、法人の有識者を別法人へ出向させることが可能になり、小規模事業者だけでは叶わなかった業務を担うことができるようになります。
⑤ 人材確保等業務- 社員合同での採用募集
- 出向等社員間の人事交流の調整
- 賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整
- 社員の施設における職場体験、現場実習等の調整
- 社員合同での研修の実施・ 社員の施設における外国人材の受け入れ支援等
社員の研修や職場体験などを合同で行うことで、ノウハウの共有やコスト削減をおこなうことが可能になります。
出典:厚生労働省 社会福祉連携推進法人制度について
このように、合併・事業譲渡だけではなく、社会福祉法人には社会福祉連携推進法人の創設という選択肢もあることをご紹介させていただきました。
また、M&Aとは異なる考え方になるのですが、社会福祉法人の理事長にとっては、「役員の交代による承継」という選択肢もあると考えられます。たしかに、社会福祉法人は営利を目的としない法人であり、経営者が出資持分を有しているわけではないため、法人そのものを売買することはできません。ただ、法人の公益的な性格を維持しつつ経営を安定させる観点からは、外部の人材が理事会に加わって支援を行ったり、経営陣を交代して運営を他の者に任せたりする方法もあるという指摘があります
(東京弁護士会 親和全期会編「Q&A各種法人の事業承継の実務」新日本法規・264頁)。
当センターでは、社会福祉法人のM&A経験があるアドバイザーが多数在籍しておりますので、ご質問などお気軽にご相談ください。
期待される効果
厚生労働省から、社会福祉法人の合併・事業譲渡マニュアルが発表されており、社会福祉法人が合併、事業譲渡等をおこなうことを、地域における福祉サービスを持続し発展させて、地域への貢献活動等を行っていくために有効であるとしています。
同じく厚生労働省が発表しているガイドラインにおいて社会福祉法人の事業譲渡等で期待される効果として、下記のようなものがあげられています。
- 法人が一体となり、本部機能や財務基盤が強化されることにより、事業の安定性と継続性が高まり、建物の修繕や設備の増強など、サービスの質の向上に 向けて積極的に設備投資を行うことが可能となることが考えられる。
- スケールメリットを活かした、資材調達などのコストを削減することが可能となることが考えられる。
- 相手方の法人の人材、ノウハウ、設備等資源を活用することにより、既存の資源の補完や高度な活用が促され、サービスの質の向上などが期待される。
- これまでにない新たな種別の施設を取り入れた場合には、提供するサービスの幅が広がることが期待される。
- 互いの法人が有機的に結合し、職員間の意識が刺激されるなど新たな法人風土を醸成することが期待される。
- 新たな領域の知識・技能・経験を持った職員を確保することができ、職員間の人事交流が促進されれば、各職員のスキル拡大・向上を図ることができることが期待される。
- 規模拡大によって教育への投資が促され、外部講師の招へいや外部研修への参加機会の確保など、充実した教育を受けることが期待される。
出典:厚生労働省 「合併・事業譲渡等マニュアル」
:厚生労働省 「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」
社会福祉法人M&Aのポイント
社会福祉法人の将来の選択肢と効果が分かったところで、実際に気を付けるべきポイントはどのような点でしょうか。
社会福祉法人のM&Aでは、社会福祉法に定められた手続きを行う必要があります。
また、持分や配当がなく、残余財産は他の社会福祉法人又はその他学校法人、公益財団法人等の社会福祉事業を行う者に帰属し、処分されない財産は国庫に帰属すると定められているため、進め方についても注意が必要です。理事・評議員等は社会福祉法人と委任の関係にあるため、その後の法人運営に大きく影響する点を踏まえ、十分な時間をかけて検討を行う必要があります。
- ① 持分がない
- ② 特別の利益供与の禁止
- ③ 行政への相談が必要
- ④ 理事会の承認が必要
特に合併や事業譲渡の場面では、新たな役員体制の構築や報酬体系の見直しが行われることが多いため、こうした規定に抵触しないよう、事前の制度理解と慎重な設計が不可欠です。
まとめ
ここまで、社会福祉法人のM&Aについて私の経験を交えながらお伝えしてきましたが、社会福祉法人のM&Aは注意すべきポイントが多く、特に譲渡のご経験がない理事長にとっては進めることが難しい内容だと思います。一般的なM&A仲介会社は、株式会社の案件の取り扱いはあっても、社会福祉法人の取扱実績が少なく、知識や経験が浅い場合もあるので、社会福祉法人のM&Aでは特に、仲介会社選びにご注意ください。
当センターは介護・障害福祉・保育業界に特化しており、社会福祉法人のM&A経験が豊富です。また当社が主催する介護福祉業界最大級の展示会CareTEXで築いたネットワークを活用し、株式会社・社会福祉法人ともに最適なマッチングをサポート可能です。
事業の今後を考え始めた理事長の皆様、是非当センターにご相談ください。




 太田丈史
太田丈史