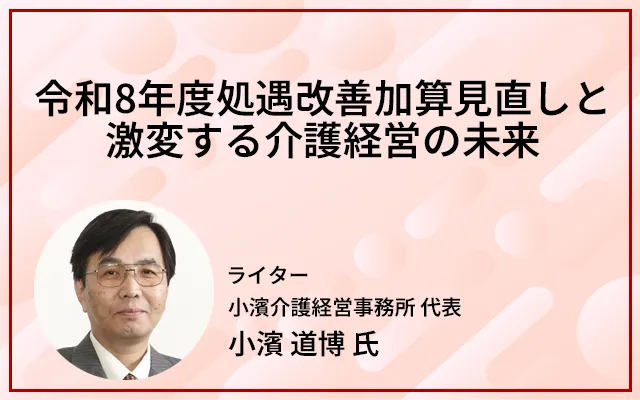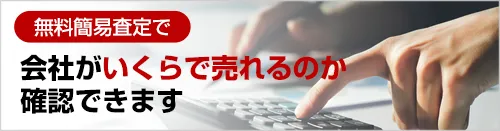令和8年度の介護職員等処遇改善加算の見直しが現実味を帯びてきた今日、介護事業を取り巻く環境はかつてないほどの大きな変革期を迎えている。処遇改善加算の改定に加え、介護DXの本格化、ケアプランの有料化、そして深刻化する人材不足への対応など、経営者が直面する課題は多岐にわたる。これらの変化をいかに的確に捉え、経営戦略に落とし込むかが、今後の事業の成否を分けることになる。情報に先んじて対応する覚悟が今こそ求められているのである。
1. 令和8年度処遇改善加算改定の確実性と背景
令和6年度、介護職員等処遇改善加算は一本化されたが、令和8年度以降の対応については実態把握を踏まえて検討するとされ、結論が先送りされていた。しかし、今年6月13日に閣議決定された「骨太の方針2025」において、医療・介護分野の「公定価格の引き上げによる処遇改善」が明確に記載されたのである。この「公定価格」とは介護報酬を意味し、来年4月からの処遇改善加算の引き上げがほぼ確実となったことを示唆している。9月から給付費分科会で審議が始まり、12月までには令和8年度の処遇改善に関する結論が出される見込みだ。最低賃金の引き上げが介護事業所の経営を圧迫している現状から、来年4月を待たずして今年度中の引き上げを求める声も上がっている。
この処遇改善の見直しが急がれる背景には、介護業界が抱える深刻な人材不足と他産業との賃金格差がある。一般産業では平均5.25%の賃上げが行われているのに対し、介護職の処遇改善による賃上げは2.5%にとどまっており、この差は人材確保の大きな足かせとなっている。介護職の有効求人倍率は4.8倍にも達し、特に訪問介護ヘルパーは15倍という異常な数値を示している。さらに、2026年には介護職が25万人、2040年には57万人も不足すると予測され、職員の離職理由には人間関係、給与の低さ、将来への不安などが多く挙げられることから、処遇改善は人材確保と定着のために不可欠な要素となっている。来年度の見直しでは、加算率のさらなる引き上げが期待されるだけでなく、生産性向上への取り組みがより一層、要件として強化される可能性が高いと認識しておくべきだ。現在、処遇改善加算の上位区分(加算IまたはII)を取得している事業所は全体の8割に上るものの、訪問介護のように小規模事業所が多い分野では加算率が低い傾向にある。事業所は上位区分の取得とともに、職員のキャリアパスを明確にする「富士山型」や「三脈型」といったモデルの構築を通じて、職員のモチベーション向上と定着を図っていく必要がある。
2.生産性向上の実践
来年度の見直しでは、加算率の引き上げに加えて生産性向上への取り組みが要件として強化される可能性が高い。生産性向上は、職員の業務負担を軽減し、利用者に寄り添う時間を増やすことでケアの質を高めることを目的としている。生産性向上の具体的な取り組みとしては、業務改善の体制構築(生産性向上委員会の設置など)や、現場の課題の「見える化」(課題分析)が挙げられる。これらの取り組みは、職員一人ひとりの負担を軽減し、利用者と向き合う時間を増やすことにつながる。
AIの活用も業務効率化の強力なツールとして注目されている。例えば、会議の議事録作成や日常の記録業務において、音声入力システムやAIを活用することで、これまで数十分かかっていた作業が数分で完了するようになる。多言語対応が必要な外国人材の現場では、AI翻訳ツールが業務マニュアルや申し送りの翻訳に活用され、コミュニケーションの円滑化と事故リスクの低減に貢献するだろう。ただし、AIは嘘をつくことがあるため、加算の算定要件など専門的な内容については、専門家による確認が不可欠であることに留意すべきだ。
また、介護助手制度も生産性向上の一環として重要である。直接的な身体介助を伴わない周辺業務(食事の準備・片付け、掃除、洗濯、見守り補助など)を介護助手が行うことで、介護職員は利用者への直接的なケアに集中できるようになる。これは介護現場の人材不足解消と、介護職員の負担軽減に繋がり、結果的に質の高いケアの提供に貢献する。

3. 持続可能な介護経営に向けた地域連携と変革への対応
介護保険制度は財政ひっ迫の状況にあり、令和9年度の介護保険法改正では、ケアプランの有料化や自己負担割合の見直し(2割負担対象者の拡大など)が検討されている。これらは利用者負担の増加を意味し、サービス利用控えに繋がる可能性もあるため、経営戦略に影響を及ぼすだろう。
また、介護サービス提供体制の地域差に対応するため、都道府県ごとに3つのエリア(中山間地、大都市部、一般市)に区分し、それぞれに合わせた配置基準の弾力化などが検討されている。これにより、介護保険制度はさらに複雑化する可能性があり、事業所は自らの所在地の特性を理解し、対応を迫られることになる。
近年、介護事業所の倒産件数は増加傾向にあり、物価高騰、人材不足、そしてリハビリ特化型デイサービスへのニーズ変化などに対応できなかった事業所が苦境に立たされている。特に小規模事業所は、事務負担、ICT化への対応、人材確保といった課題に単独で対応することが困難なケースが多い。
このような状況を打開するため、地域での「小規模事業所グループ」形成による連携・共同実施が有効な戦略となる。複数の事業所が協力し、共同で研修を行ったり、ICT導入のノウハウを共有したり、外国人材の育成を共同で行うことで、個々の事業所の負担を軽減し、大規模法人と同等のマネジメント体制を構築することが可能となる。さらに、介護助手、元気な高齢者、障害者、LGBTQ+など、多様な人材の活用を積極的に進めることも、人材確保の鍵となる。
この変革期は、私たち介護事業経営者にとって「ピンチをチャンスに変える」絶好の機会である。常に情報にアンテナを張り、変化を恐れず、戦略的に対応していく覚悟が今こそ求められている。令和8年度の処遇改善加算の見直しと、介護DX、そして制度全体の変革の波を的確に捉え、質の高い介護サービスの提供と持続可能な経営の実現に向けて、今すぐ行動を起こすことが、私たち自身の、そして日本の介護の未来を切り拓く鍵となるに違いない。




 小濱 道博 氏
小濱 道博 氏