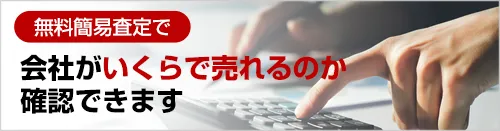【目次】
はじめに:介護経営者が直面する現実と、M&Aが選択肢となる理由
介護業界を取り巻く経営環境は、年々厳しさを増しています。慢性的な人手不足、後継者不在、報酬改定による収益性の不安定さ──これらの課題に直面する経営者は少なくありません。
とくに2024年度の介護報酬改定では、処遇改善が進められた一方で、事務負担の増加や物価高騰とのギャップにより、「このままでは経営が続けられない」と感じる事業者が増えています。
そうした中、改めて注目されているのが「M&A(企業の合併・買収)」を活用した経営戦略です。M&Aというと「売却」や「撤退」のイメージがつきまといますが、それは誤解です。M&Aは、「守り」の選択肢であると同時に、「攻め」の経営にも転じうる強力なツールでもあるからです。
根拠データ:後継者不在率は依然50%超
2024年11月に公表された帝国データバンクの「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」によれば、後継者が「いない・未定」とする企業の割合は52.1%にのぼり、依然として半数以上が後継者不在の状況にあります。
介護事業は地域にとって生活インフラでもあります。経営者がいなくなれば、利用者や職員、さらには地域全体が大きな影響を受けかねません。だからこそ、M&Aは事業を手放すものではなく、介護サービスを未来へと継続させるための「責任ある経営判断」として、経営者に求められています。
第1章:なぜ今、介護業界にM&Aが必要なのか?
高齢化社会が進む中で、介護サービスの需要は今後も伸びると予測されています。しかし、それを支える介護事業者の経営は、決して安定しているとは言えません。
とくに後継者の不在は、業界全体の構造的な課題となっています。経営者の体調不良や急な引退によって、事業の継続が困難になるケースも少なくありません。そしてその結果、職員や利用者に直接的な影響が及ぶことになります。
介護事業は、地域の暮らしを支える存在です。一つの事業所がなくなることで地域の生活基盤が揺らぎかねないからこそ、事業を守り続けるための手段として、M&Aの活用が今強く求められています。
第2章:M&Aは“守り”と“攻め”の経営戦略
M&Aは「後継者がいないから仕方なくやるもの」ではなく、目的と準備次第で“戦略的な経営手段”になります。
◆ 守りのM&A:地域と事業を守る
・後継者不在の状態から脱却できる
・職員や利用者に混乱を与えず、サービスを継続できる
・地域で築いた信頼や仕組みを、次の組織にバトンとしてつなげられる
実際、弊社が支援した訪問介護事業所では、60代前半の代表者が「現場は好きだが経営の負担が重い」と悩んでおられました。同地域の福祉法人にM&Aで譲渡し、職員と利用者は全員継続。代表者も一定期間アドバイザーとして関与しながら、円満な引退を迎えることができました。
◆ 攻めのM&A:成長と拡大
・他地域への展開を加速させる
・通所・訪問・施設などの多機能化を進める
・専門性の異なる法人を統合して、差別化されたサービスを実現する
こうした“攻め”のM&Aは、単なる買収・売却ではなく、「お互いの強みを活かして、次のステージに進む」という考え方です。

第3章:M&Aを“経営の武器”として使うための準備
M&Aを成功させるには、最低限以下の3つの視点が必要です。
1. 財務の整理と可視化
決算書3期分の整理や借入・リースの状況を明確にしておくことが重要です。利益が出ていない場合でも、地域密着性や職員の定着率、人材力といった“数字に現れにくい価値”が評価されることもあります。
2. 運営体制・コンプライアンスの整備
帳票・マニュアル・勤怠管理の整備、指導監査への対応状況など、「日常業務がどのように行われているか」が見える形にしておくことが求められます。
3. 理念・ビジョンの言語化
どんな想いで事業を続けてきたのか?
どんな未来を地域や職員に届けたいのか?
これらが明確になっていることで、M&Aの相手法人との“理念の相性”が良くなり、よりよい形での承継が実現します。
また、自分での整理が難しい場合は、介護の専門家やM&Aの専門家と一緒に取り組むことでスムーズに進めることができます。
第4章:未来を切り開くために、今できること
東京商工リサーチの調査によれば、2023年に老人福祉・介護事業で発生した倒産は122件、休廃業・解散は510件に達し、いずれも過去最高水準となっています。
こうした背景には、人件費や物価の高騰といった外的要因に加えて、経営者の高齢化や後継者不在、経営体制の属人化といった内部要因が複雑に絡み合っていると言われています。つまり、準備不足のまま経営を続けてしまった結果、やむなく事業継続が困難になったケースが増えているのです。
しかしM&Aを「責任ある経営判断」として選択すれば、「介護を続けるために必要な次の一手」になります。
いざというときに慌てて対応するのではなく、今から少しずつ準備を始めることで、選択肢の幅が広がります。後継者が社内外にいない場合や、法人としての今後に迷いがある場合でも、M&Aという手段を知っておくことは、将来にわたって事業を守る大きな力となります。
まとめ:M&Aは経営戦略の一つ
M&Aは、事業を手放す手段ではありません。
それは、事業の継続性を高め、地域の暮らしと職員の雇用を守る選択肢であり、経営者が築き上げてきた想いを引き継ぐ手段です。
同時にM&Aは、事業を大きく展開し、可能性を広げるための“攻めの経営ツール”でもあります。多機能化・地域拡大・サービスの高度化など、単独では難しい挑戦を、連携によって実現する力がM&Aにはあります。
つまりM&Aは、“終わらせるための一手”ではなく、“続けるための、そして成長するための一手”です。
介護経営者としての責任を果たしながら、未来を描く視点を持つためにも、M&Aという選択肢を今から準備しておくことが、何よりも重要なのです。




 片山 海斗 氏
片山 海斗 氏