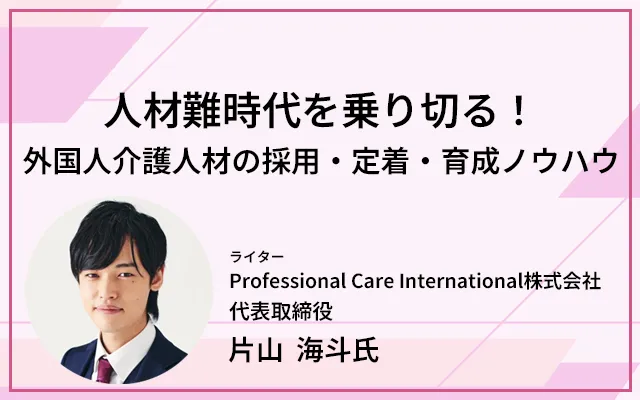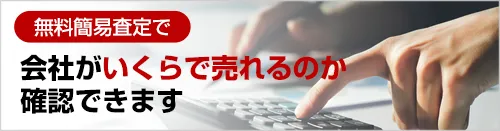深刻な人手不足が続く介護業界。厚生労働省の推計では、2040年には約69万人の介護人材が不足するとされています。
現場では「求人を出しても応募がない」「採用しても続かない」という声が日常的に聞かれ、人材確保が経営を左右する時代に突入しました。その中で注目されているのが、外国人介護人材の活用です。外国人採用というと「ハードルが高い」と感じる方も少なくありませんが、制度を正しく理解し、受け入れ体制を整えれば、彼らは介護現場を支える大きな戦力になります。
本コラムでは、介護事業者が押さえるべき「外国人採用の仕組み」「定着のための工夫」「共に育つ職場づくり」まで、経営者・管理者の視点でわかりやすく解説していきます。
介護業界の人材不足と外国人受け入れの背景
政府が外国人介護人材に目を向けた背景
介護をはじめとする福祉の仕事は、人の尊厳と暮らしを支える社会に欠かせない存在です。どんなに時代が変わっても、「人が人を支える」という営みは決して失われません。しかし、国全体の経済構造の中では、福祉分野は経済成長や税収を押し上げる産業ではないという現実があります。さらに、介護需要は2040年前後をピークに減少していく見通しであり、政府も業界が数十年後、縮小していくことを認識しています。
そのため、政府は、今は需要が高く必要とされていても、労働人口が減少する中で闇雲に日本人を多く介護分野に配置し続けると、経済成長が鈍化し、ピーク後の失業率や税収減少につながる恐れがあると考えているのです。
こうした背景から、政府は「限られた人材をどう活用するか」という視点で、介護人材確保を短中期的な政策課題として位置づけ対策を練ってきました。
その結果、社会保障制度を維持するための“つなぎの政策”である、現実的かつ即応性のある人材として外国人介護人材の受け入れを推進するようになったのです。
外国人採用は、避けては通れないテーマ。まずは関わるところから。
介護事業のみならず、外国人材の採用は巷でもよく聞き、都会のコンビニではほとんど外国人スタッフのところもあります。急によく見かけるようになっただけに、外国人に関する様々な文化衝突や事件が目につき、「移民」や「外国人」と聞くとネガティブなイメージを想起する人もたくさんいます。
しかし、相手は文化や言語が違うだけの、同じ人間です。働いているところをみてみると、真面目に仕事をして、良いケアをしていた、という例はたくさんあります。特に、介護の制度で現在働いているほとんどの外国人の方々は、外国の地で働けるほどの努力家です。まずは、憶測や噂で判断せず、実際に関わってみましょう。
外国人介護人材の採用で押さえるべきポイント
外国人介護人材の受け入れ制度の全体像
外国人が日本で介護職として働くには、厚生労働省が定める4つの在留資格があります。
「特定活動(EPA)」「技能実習」「特定技能」「在留資格『介護』」の4種類で、それぞれ目的や仕組み、働ける範囲が異なります 。
どの制度を活用するかは、事業の規模・サービス形態・採用目的によって変わり、例えば歴史があり受け入れ実績の多い制度もあれば、即戦力として活用しやすい制度もあります。
自社にとってどの制度が適しているかを見極めるには、制度の運用を熟知した専門家や登録支援機関へ相談するのが安心です。
また、制度そのものよりも大切なのは、採用した職員が安心して働き続けられる環境を整えること。制度は“入口”であり、採用の成功を分けるのは自社の受け入れ体制です。
登録支援機関の選び方
外国人介護人材の採用を進めるうえで、まず押さえておきたいのが登録支援機関の選定です。どんなに良い制度を使っても、支援体制が整っていなければ人材は定着しません。
登録支援機関は、採用から受け入れ、就労・生活のフォローまでを支える事業所のパートナー。
経営者としてチェックしておきたいポイントは、次の3つです。
① 契約内容(支援範囲と費用の確認)
まず確認したいのは、契約の中身が明確かどうか。支援内容や費用、緊急時の対応範囲が曖昧なまま契約すると、後々トラブルの原因になります。
「支援一式」「随時対応」といった表現は要注意です。
特に見ておきたいのは次の3点。
・サポートの範囲:手続き・通訳・生活支援など、どこまで対応するのか
・費用の内訳:サポート料や通訳費などが明確になっているか
・緊急対応:夜間や休日のトラブル時に連絡できる体制があるか
契約は、単なる書類の取り交わしではなく、責任と役割を明確にする約束です。
不明点を残したまま進めないようにしましょう。
② 実績(過去の支援と現場理解)
登録支援機関を選ぶときは、数より中身を見ることが大切です。「導入実績○○件」といった数字だけではなく、その後の定着率や離職率まで確認すること。
採用人数が多くても、すぐに離職してしまうようでは意味がありません。
また、どんな施設や事業所をサポートしてきたのか、実際にどんな課題を解決してきたのかも確認しましょう。現場での課題解決の積み重ねこそが、良い支援機関の証です。
③ フォロー体制(採用後のサポート)
採用後のサポート体制がしっかりしているかどうかも重要な判断材料です。
登録支援機関は、外国人職員が現場に定着できるように支援する立場です。生活面の相談、通訳支援、定期面談の有無など、サポートの中身を具体的に確認しておきましょう。
夜間や休日など、トラブルが起きやすい時間帯に連絡できる体制があると安心です。また、日本人職員へのアドバイスや、文化・言語の違いをフォローしてくれるかどうかも大切なポイントです。
登録支援機関は“任せる相手”ではなく、共に職員を支えるパートナー。
事業所と同じ方向を向いて動いてくれるかどうかが、最終的な決め手になります。
面接では「介護への思い」を見る
外国人介護人材の面接では、語学力や経験を重視しがちですが、本当に見るべきなのは介護に対する思いと人柄です。
語学や技術は日本で働きながら身につけられますが、人の内面や価値観は簡単には変わりません。
異国の地で働くというのは、大きな覚悟が必要です。
「なぜ日本で介護をしたいのか」「どんなことを学びたいのか」――
その人の言葉から、仕事への姿勢や誠実さ、覚悟を感じ取ることが大切です。

定着と育成──辞めない職場をつくる
外国人職員を受け入れる環境づくり
外国人職員が定着する職場は、例外なく「受け入れ準備」ができています。日本語や文化の違いを前提に、最初から“わかりやすく伝える仕組み”を整えているのです。まず大切なのは、やさしい日本語で伝えること。専門用語や曖昧な表現を避け、「短く・具体的に・一文一情報」で話す。例えば「ちょっと」「そろそろ」「いい感じ」といった曖昧な表現は誤解のもとなので避けるのが無難です。
次に、目で見て分かる仕組みを取り入れましょう。
業務マニュアルや指示書は、写真やイラストを多く使うだけで理解度が一気に上がります。手順を表にしたり、チェックリストを壁に貼るのも効果的です。
また、現場全体の意識づくりも欠かせません。日本人職員が「教える側」ではなく、共に働く仲間として関わる姿勢を持つこと。
宗教や文化、生活習慣の違いを尊重し、「なぜ違うのか」を理解し合う研修を取り入れると、誤解や衝突を防げます。そして、分からないことをすぐに聞ける雰囲気をつくること。質問しやすい職場は、それだけで離職率が下がります。新しい文化を受け入れる柔軟さが、結果としてチームの強さにつながるのです。
「教える」から「共に成長する」職場へ
外国人職員の定着を支えるのは、一方的に教える職場ではなく、共に学び合える環境です。その中心にあるのが、介護福祉士などの資格取得支援。資格は、外国人が日本で長く働くための条件であり、その“学び”を後押しする仕組みづくりが欠かせません。
たとえば、資格取得のための制度や補助金の整備、勤務時間内での学習サポート、オンライン研修の導入など、事業所としてできる支援は数多くあります。こうした仕組みは外国人だけでなく、日本人職員にも等しく提供することが重要です。慣れない言語や文化の中で資格を目指して勉強する外国人職員の姿は、日本人職員のモチベーションにもつながります。努力が伝わることで、お互いの意欲が高まり、「共に成長する職場」へと変わっていくのです。
教育は、感覚や経験ではなく仕組みで支える時代。進捗や習熟度を見える化し、研修・記録・書類業務を効率的に管理することで、指導側の負担を減らし、育成の質を上げられます。最近では、多言語対応の研修システムや業務管理アプリなど、教育・共有・管理を一元化できるツールを導入する法人も増えています。
“共に学び、共に支え合う”――その意識が根づけば、外国人も日本人も安心して働ける、強いチームが育つでしょう。
人を活かす経営へ
外国人介護人材の採用・定着・育成は、特別なことではありません。どの職員にも共通して大切なのは、「人を大切にする経営」です。制度や仕組みは、あくまで人を活かすための手段にすぎません。価値観、文化や言語の違いを超えて、同じ目標に向かって一緒に働ける環境があるか。その一点が、介護事業の未来を左右します。外国人職員が安心して働ける環境を整え、日本人職員と共に成長できる職場をつくることは、単なる人材確保ではなく、組織全体の価値を高める投資にもなります。一人ひとりが自分の役割を誇りに思えるチームを育てること。それが、「辞めない職場」を超えて、“人が集まり、人が育つ事業所”への第一歩です。




 片山 海斗 氏
片山 海斗 氏