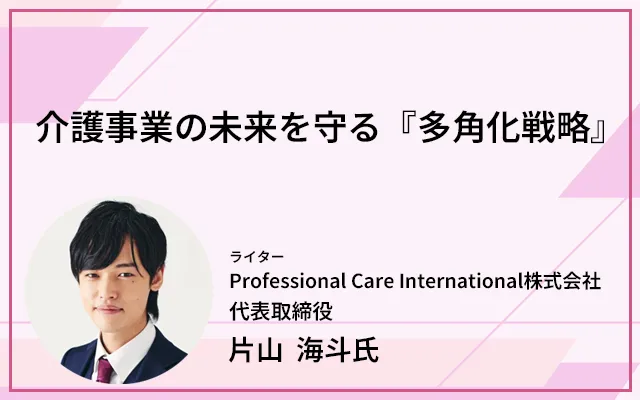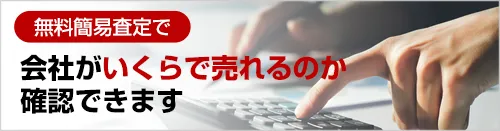【目次】
1. なぜ今、多角化が必要なのか
介護業界は「高齢化社会だから安泰」と思われがちですが、実際の経営環境は年々厳しさを増しています。
最大の要因は、3年ごとに行われる介護報酬改定です。単価や加算要件はその都度見直され、上がる場合もあれば下がる場合もあります。事業形態によっては大幅な減収につながり、収益が大きく揺れる要因となります。
加えて、運営指導のリスクも無視できません。重大な指摘を受ければ、加算取り消しや報酬返還などの形で突発的な資金流出が発生します。近年は不正請求や加算要件未達へのチェックが一層厳格化しており、経営に与える影響は軽くありません。
さらに、人材確保競争はますます激化しています。厚生労働省の「職業安定業務統計」(令和7年6月)によれば、介護職員の有効求人倍率は全国平均で3倍を超え、都市部では5倍以上という地域もあります。まさに人を「奪い合う」状態です。もし採用できても短期離職が続けば、サービス品質の低下や職員負担の増加を招き、結果として利用者離れを招く恐れがあります。
そこに追い打ちをかけるように、異業種からの参入や大手企業の進出が最近増えてきています。資本力とブランド力を背景に、地域シェアを奪っていくケースも多く、既存事業者の競争環境は一層厳しくなっています。こうした状況では、「介護サービス一本足」の経営モデルでは制度や市場の変化に耐えきれず、将来的な不安定要因を抱え続けることになります。
だからこそ今、収益源やサービス形態を複数化し、経営基盤をより強固にする多角化戦略が求められています。これは、制度改定や運営リスクへの備えであると同時に、新しい事業機会をつかむための取り組みでもあります。
2. 多角化で広がる経営の可能性
今ある資源を活かせる分野から着手すれば、低リスクで収益源を増やせます。
多角化は必ずしも大規模投資や未知の分野への挑戦を意味しません。むしろ、今ある強みや資源を生かせる分野から始めるほうが、成功しやすくリスクも抑えられます。
いくつか例をお伝えします。
介護保険外サービス 例:買い物代行、配食、見守り、介護予防教室など。
公的報酬に依存しない収入源を確保できます。特に高齢者の生活支援分野は潜在需要が大きく、地域とのつながりを深める効果もあります。
他分野への参入 例:障がい者支援、子育て支援など。
顧客層を広げ、長期的な利用基盤を形成します。福祉分野の相互連携によって、利用者のライフステージに応じた継続支援が可能になります。
周辺サービスの追加 例:福祉用具レンタル、住宅改修。
既存利用者への提案機会が多く、営業効率が高い分野です。サービスを一括提供できることで顧客満足度も向上します。
医療との連携・参入 例:訪問看護事業、リハビリ特化型サービス。
医療保険収入を得られ、サービス対象を拡大できます。介護と医療の両面から地域の在宅生活を支えられる体制は、行政や病院からの信頼を得やすい特徴があります。
重要なのは「小さく始め、需要を確かめながら広げる」こと。そして、もう一つの選択肢としてすでに軌道に乗っている事業所や法人をM&Aで取り込むのも有効です。ゼロから立ち上げるより短期間でノウハウ・人材・顧客基盤を獲得でき、成長スピードを大幅に高められます。近年は後継者不足を背景に事業譲渡案件も増えており、タイミング次第では好条件での取得も可能です。
3. 多角化の成功事例
実際に多角化を実行している企業の成功事例をご紹介します。
A社:訪問看護ステーションの開設で医療連携を強化
地方都市でデイサービスを運営するA社は、報酬改定や人材不足の影響で収益が不安定化していました。そこで看護師を採用し、訪問看護ステーションを新設。開設から3ヶ月で黒字化し、デイ利用者の体調変化にも自社対応できる体制を整備。地域の医療機関からの信頼も高まり、病院からの退院支援依頼も増加しました。
B社:障がい児向けデイサービスで顧客層を拡大
B社は既存施設の空き時間を活用し、放課後等デイサービスを開設。地域の要望が強かった分野であったため、開所直後から予約待ちの状態に。障がい児支援分野への参入により、将来的な成人後支援事業にも発展できる基盤を築きました。
C社:介護保険外サービスで利用者満足度を向上
C社は買い物代行と夕食宅配を有償化。地域スーパーと提携し、効率的な運営を実現しました。利用者や家族からは「困ったらまず相談できる存在」として頼られるようになり、口コミによる新規顧客の獲得にもつながりました。
D社:M&Aで新分野に一気に参入
D社は、地域で評判の良い障がい者グループホームを営む小規模法人をM&Aで取得。既存スタッフや運営ノウハウをそのまま引き継ぐことで、立ち上げ時のリスクを大幅に軽減。取得からわずか半年で黒字化を達成し、グループ全体の収益源を多様化しました。
4. 多角化を進める際の注意点
多角化は万能の経営策ではありません。誤った判断や準備不足など計画性がないままで進めると、本業の収益まで圧迫する危険性があります。
【多角化を進める際の注意点】
- ① 市場調査不足:地域に需要がなければ新事業はすぐに行き詰まります。
- ② 人材計画の欠如:人手不足の中で無理に事業拡大すると、サービス品質の低下を招きます。
- ③ 資金繰りへの影響:初期投資や運転資金を回収できるまでの期間を過小評価しないこと。
- ④ 運営ノウハウ不足:未経験分野は専門人材の確保や外部のサポート活用が不可欠です。
成功のためには、小規模からの試験導入や、M&Aでの即戦力確保、行政の補助金活用など、リスクを減らす仕組みを組み込むことが大切です。

5. まとめ
介護事業の多角化は、売上拡大だけでなく、制度改定や運営指導のリスクから経営を守るための重要な戦略です。
- ・自社の強みを活かす
- ・地域ニーズに合った分野を選ぶ
- ・小規模から始め、需要を確かめながら広げる
- ・必要に応じてM&Aで事業を一気に取り込む
これらを押さえれば、変化の激しい介護業界でも安定した経営基盤を築くことができます。将来の安心を確保するためにも、今こそ一歩を踏み出すべき時です。
経営の選択肢としての多角化──その第一歩は、地域と利用者に必要とされる新たな価値を生み出すところから始まります。




 片山 海斗 氏
片山 海斗 氏